財産目録を相続で必ず作るべき理由とは【メリット解説】
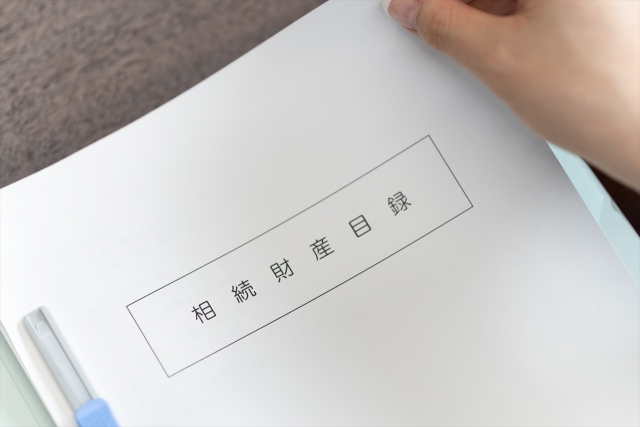
大切なご家族が亡くなられて、深い悲しみの中、相続の手続きを進めなければならない…。「何から手をつけていいかわからない」「やるべきことが多すぎて、頭が真っ白…」多くの方が、そんな不安な気持ちでいっぱいになるかと思います。
そんな、途方に暮れてしまいそうな時に、事前にあれば便利なもの、それが「財産目録」です。
財産目録とは、故人の財産のリストです。多くの場合、財産目録の作成は義務ではありませんが、相続時の負担軽減のためにも作成しておくべきものです。
今回は、この「財産目録」がなぜ必要なのか、そしてどうやって作ればいいのかを、一緒に見ていきましょう。
そもそも「財産目録」とは
財産目録とは、シンプルに言うと、「故人(被相続人)が所有していた財産のリスト」です。
財産目録に記すのは預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけではありません。マイナスの財産もすべて書き出す必要があります。
- ○プラスの財産
- 預貯金、現金
- 土地や建物などの不動産
- 株式や投資信託
- 車、貴金属といった動産
- ゴルフ会員権など
- ○マイナスの財産
- 住宅ローンやカードローンなどの借金
- 誰かの借金の保証人になっている場合の債務
- 未払の家賃、水道光熱費、医療費など
- 未払いの税金
- 事業上の買掛金や手形債務など
借金もリストに入れるの?と驚かれるかもしれません。しかしながら、相続ではマイナスの財産も引き継がれます。もし、プラスの財産だけを見て相続を決めてしまい、後から大きな借金が見つかったら大変ですよね。
財産目録は、そうした「知らなかった…」という事態を防ぎ、ご家族が「相続するのか、それとも放棄するのか」を冷静に判断するための、大切な判断材料にもなってくれるのです。
財産目録作成のメリット
(1)全ての財産が明らかになる
相続ではまず、すべての財産を把握することがスタートです。
遺言書で配分が指定されていなければ、法定相続人同士で財産の分配について協議しますが、財産が不明のままでは、話し合えません。
また、相続人間で疑いの気持ちも生まれてしまいます。『兄貴だけ、何か隠してるんじゃないか…』『本当はもっと預金があったはずでは…』等々、財産の全体像がハッキリしないせいで、争いのきっかけになってしまうこともあります。
その点、財産目録があれば、全員が同じリストを見ながらオープンに話し合いができます。「隠し事はない」という透明性が、互いの信頼関係を守り、円満な話し合いの土台を作ってくれるのです。
なお、全ての財産が明らかになっていれば、相続放棄を選ぶ指標にもなります。
前述したように相続ではマイナスの財産も取得します。よって、目録があると、遺産を相続した際に損失が出るかがすぐにわかります。
(2)相続手続きをスムーズにする
相続では、銀行での預金解約や、法務局での不動産の名義変更など、色々な手続きが必要です。そのため、財産の情報をまとめておかないと、時間も手間もかかってしまいます。
逆に財産目録があれば、必要な情報がすぐに分かり、面倒な手続きがスムーズに進みます。
(3)遺言書がよりわかりやすくなる
遺言書を作成の際には、財産目録を作成しておくべきです。
遺言書には財産の分配方法や内容について書きますが、財産目録があれば、遺言者・受遺者共に財産を把握できて便利だからです。
財産目録は誰が作るのか
財産目録は誰が作成しても構いませんが、相続手続きがスムーズになるように被相続人が生前に作成しておくと良いでしょう。
財産目録と遺言書があれば、相続手続きはかなり楽になります。
被相続人が目録を作成していない場合は、相続開始後に中心的に手続きを進めていく相続人が作成する場合が多いです。
目録作成が必須のケースもある
基本的には「作ったほうがいい」財産目録ですが、以下のケースでは作成が必須となっています。
- 裁判所で遺産の分割について話し合う(遺産分割調停)とき
- 遺言書で「遺言執行者」が指定されているとき
遺産分割の調停の場合、家庭裁判所に財産目録を提出します。また、遺言書で遺言執行者が指定されていると、遺言執行者は相続人に交付するための財産目録を作らなければなりません。
目録作成時のポイント
(1)誰が見てもわかるように「具体的」に書く
例えば、預金なら「〇〇銀行の預金」だけでは不十分。「〇〇銀行 △△支店、普通預金、口座番号12345、残高〇〇円」というように、手続きする人が迷わないように詳しく書きましょう。
不動産なら、権利証(登記識別情報)や固定資産税の納税通知書を見ながら、正確な情報を書き写しましょう。
(2)「抜け漏れ」がないように、しっかりチェック
もし、目録を作った後に新たな財産が見つかると、せっかく終わった遺産の話し合いを、もう一度やり直さなければならなくなります。それは、相続人にとって大きな負担です。
よって、目録へは記載漏れがないように気をつけましょう。
まとめ
財産目録があるだけで、相続時の手続きがまったく違ったものになります。財産目録があることで遺産が明確になるので、相続人は無用な混乱に巻き込まれずに済むのです。
相続税についても目録を元に申告書を作成できますので、手間が省け、申告漏れも防ぐことができます。
なお、「財産の種類が多くて、どこから手をつけていいか分からない」「忙しくて、調べる時間がない…」という方も、たくさんいらっしゃると思います。
そんな時は、相続の専門家に財産の調査と作成をご依頼ください。専門家に頼むことで、時間の削減と安心を得られます。具体的なお話が聞きたい場合、まずはご相談ください。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。
初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。
お電話での対応は[048-592-5533] 受付時間9:00〜18:00です。
メールは[こちら]まで 24時間受付中。

平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。
