遺言執行者ができる手続きとは!? 相続税の申告もできるのか
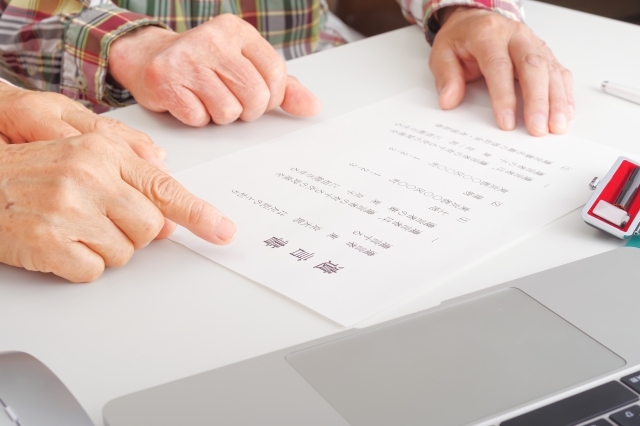
遺言書は、遺言者の思いや意志を、相続という形で具体的に反映させるための大切な手段です。その実現を担うのが「遺言執行者」と呼ばれる人です。遺言に書かれた内容に従って、必要な手続きを行っていく役割を担います。
遺言執行者には、遺産の管理や処分など、遺言の実現に必要な範囲で、法律上の権限と義務が認められています。
こう聞くと、遺言執行者が相続に関するほとんどのことを代行できるのではないか?と思うかもしれません。しかし実際には、できることとできないことがあります。
とくに気をつけたいのが、「相続税の申告」です。時間も手間もかかるこの手続き、遺言執行者にお願いできるのでしょうか?
遺言執行者を立てる意味とは
遺言執行者とは、遺言書の内容をきちんと実現させるために活動する人です。相続人や受遺者の代理人として動くことができ、手続きの円滑化に一役買ってくれます。
例えば、複数の相続人がいるケースでは、各自が書類に署名・押印したり、必要書類を集めたりするのはなかなか大変です。しかし、遺言執行者がいれば、その人が代表として手続きを進められるため、相続人の負担を大きく減らすことができます。
また、遺言執行者を選任しておくことで、不動産の名義変更を放置することを防いだり、他の相続人が勝手に財産を処分するのを抑止したりする効果もあります。
執行者は、相続人の中から選んでもいいですし、それ以外の第三者でも問題ありません。未成年者や破産者といった法律上の欠格事由に該当しない人であれば、誰でも就任可能です。
遺言執行者ができること・できないこと
遺言執行者に認められている主な業務は、以下のようなものです。
- 執行者に就任した旨と、遺言の内容を相続人へ通知すること
- 被相続人の戸籍を調べ、相続人を確定させること
- 相続財産の調査と目録の作成
- 遺言に従った手続きの実施(不動産登記、預金の解約・払戻しなど)
これらの手続きは、遺言書の内容に基づいて動くものなので、執行者が行うことができます。
一方で、「相続税の申告」については、遺言執行者であっても行うことができません。
というのも、相続税の申告・納税義務は、財産を実際に受け取る相続人や受遺者に個別に課されているからです。執行者が代理で申告する権限は認められていません。
相続税の申告は、相続が始まったこと(=死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。申告が遅れると、延滞税や加算税が課されることもあるため、注意が必要です。
遺言執行者にしかできないこともある
執行者にしかできない手続きもあります。代表的なのが次の3つです。
- 子の認知…遺言によって非嫡出子(婚外子)を認知することができますが、その手続きは遺言執行者が行います。認知届の提出は、就任から10日以内に行わなければなりません。
- 推定相続人の廃除またはその取消し…推定相続人に、著しい非行や虐待、侮辱などがあった場合、遺言によって相続権を剥奪することができます。この手続きの実行も、執行者の役目です。厳密にはこの手続きについては、他の相続人でもできますが、執行者を指定しておく方が望ましいと言えます。
- 特定遺贈の実行…遺言によって特定の人に不動産などの財産を贈与する場合(特定遺贈)は、執行者が登記などの実務を担います。これは民法の改正によって、執行者だけができる手続きと明記されました。
専門家に執行者を依頼するメリット
遺言執行者は誰でも選べるとはいえ、実際には弁護士や司法書士、税理士といった専門家に依頼するケースも多く見られます。
相続は多くの人にとって初めての経験ですし、必要な手続きが複雑で分かりにくい場面もあります。その点、相続のプロに依頼すれば、手続きがスムーズに進み、ミスや遅れの心配も少なくなります。
さらに、家族や親族間のトラブルを防ぐという面でも、専門家が中立的立場で動いてくれることは大きな利点です。感情的になりやすい相続の場面で、相続人の一人が執行者になることで軋轢が生まれてしまうこともあります。
もちろん、専門家に依頼する場合は報酬が発生します。しかし、費用以上の安心感や効率性が得られる可能性は高いでしょう。いくつかの事務所に相談し、信頼できるところを選ぶことをおすすめします。
まとめ
遺言執行者は、遺言内容の実現に向けて必要な手続きを進める大切な役割を担います。ただし、相続税の申告だけは相続人や受遺者にしかできないため、注意が必要です。
トラブルを避け、スムーズな手続きを目指すなら、遺言書の作成時に遺言執行者の指定も検討しましょう。
そして、可能であれば、相続の専門家に依頼するのも一つの安心材料になります。
相続手続き・相続税対策・遺言書作成・生前贈与など、相続に関するお悩みは(株)FP財産総合研究所までご相談ください。
年に数回、北本市役所にて税務相談員を受け持っている経験豊富な税理士が対応させていただきます。
初回の相談は無料なので、是非ご利用ください。
お電話での対応は[048-592-5533] 受付時間9:00〜18:00です。
メールは[こちら]まで 24時間受付中。

平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。
